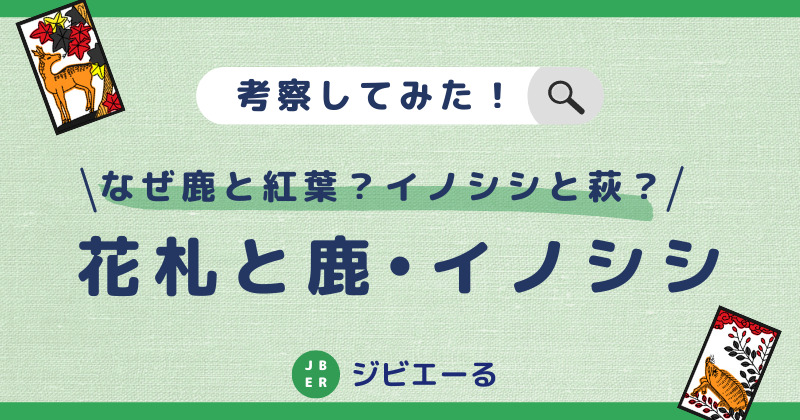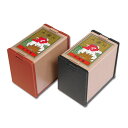こんにちは!
編集長のあかりんご(@akaringo252588)です!
「こいこい!」
…と聞くと皆さんお分かり、そう、今回は花札についての記事です。
花札に鹿とイノシシが描かれている絵札があります。
そう、「鹿に紅葉」と「萩にイノシシ」ですね。
これらはそれぞれ、7月と10月の絵札になります。
ですがなぜ7月はイノシシで、10月は鹿なのでしょう。
今回はその花札の絵札に関する考察記事となっています!
あくまで私の意見なので、皆さんもSNSで記事をシェアしご自身の意見をお聞かせくださいね!
花札と関連が深い野生動物

花札が生まれたのは、安土・桃山時代。
当時流行っていた天正かるたがもととなり、江戸中期には現在の花札になりました。
花札は、場に絵札を出していき、役を作るゲームです。
役とはカードの組み合わせのこと。
例えば「すすきに月」のカードと「菊に盃」のカードを合わせると「月見で一杯」となりポイントが入ります。
これを覚えるまでが難しいんだよねぇ
花札の絵札は12種類で、札は月ごとに4枚、合計48枚のカードを使います。
それぞれに月々の風物が描かれています。
例えば1月なら松に鶴、3月なら桜に幕といった感じです。
どれも華やかで、見てるだけで楽しい…!
10月の札は紅葉に鹿

花札の10月の絵柄に描かれているのが「紅葉に鹿」。
この絵札では、赤と黄色と黒の混じった紅葉とそっぽを向いた鹿が描かれています。
他人から無視されることをシカトと言いますが、これは花札が由来だとされています。
花札に描かれている鹿は無愛想にそっぽを向いているからです。
この鹿が描かれている絵札は10月であることから、「鹿10」→「シカト」が生まれたのです。
7月の札は萩に猪

7月の絵札に描かれているのが萩(はぎ)に猪です。
小さな赤い実をたくさんつけた萩の上に、イノシシが腰を下ろしています。
そしてイノシシは少し上を見上げるように鼻を高く上げており、人間のような目が描かれています。
ギョロッとした目付きがちょっと怖いですね…。
同じ江戸時代に描かれた絵にあるイノシシも、ギョロッとした目付きが特徴的です。
この時代の人が捉えていたイノシシってこんな感じだったのか…
なぜ鹿と紅葉、イノシシと萩なのか?
それでは、なぜ鹿と紅葉、イノシシと萩が一緒に描かれることになったのでしょうか?
いくつか仮説となるお話があるので、紹介していきます。
三作少年と鹿の悲しい物語
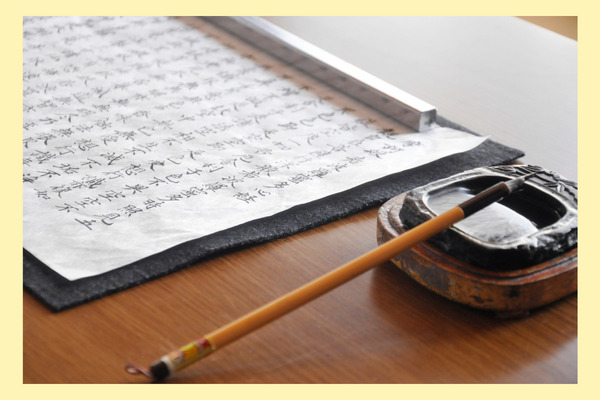
鹿と紅葉が描かれるようになった理由は何だったのでしょうか?
一つの仮説として、近松門左衛門の浄瑠璃「十三鐘」にこのようなお話があります。
江戸時代、奈良の寺子屋で習字を習っていた三作。
そこへやってきた鹿は縁側に上がり込み、書道道具を加えて持ち去ろうとします。
三作はそれを阻止しようと文鎮を鹿に投げつけますが、打ち所が悪くて鹿は死んでしまったのです。
当時、奈良の鹿は神の鹿、つまり神鹿(しんろく)として大切に保護されていました。
三作はまだ小さな子供でしたが神鹿を殺した罪は免れまられせん。
よって生きたまま埋められる刑に処されてしまいます。
母親はせめてもの弔いにと、三作が埋められた所に紅葉を植えました。
ここから、鹿と紅葉が一緒に描かれるようになったと言われています。
子どもを生き埋めにするなんて…!?
それくらい鹿というものは奈良では神様だったんですね。
石の当たりどころが悪かっただけ…でも神様のメンツを守るためにも子どもを罰しなければならない。
そんな人々の葛藤や、この時代の残酷さがこのお話に詰まっている気がします。
なぜ鹿が神様として扱われるようになったのか気になった方は、この記事をチェックしてみてください!

百人一首にも「紅葉と鹿」

そしてもう一つ、紅葉に鹿と聞くと、こちらの百人一首を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
奥山に もみじ踏みわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ 秋は悲しき
猿丸太夫(5番)『古今集』秋上・215
これは百人一首にある和歌です。
訳:人里から離れた奥山で、散ってしまった紅葉を踏み分けながら雌鹿を求めて鳴く鹿の声を聞く時こそ、いよいよ秋は悲しいものだと感じられる。
メス鹿を求めて鳴くオス鹿の声を聞いて、しんみりと悲しい気持ちになる作者の心情が伺えます。
こちらも鹿と紅葉が一緒に描かれた和歌です。
平安時代の歌人が詠んだ和歌ですから、三作の物語ができるずっと前になります。
このように鹿と紅葉の組み合わせは、日本の文学を見ても様々なところで見られることが分かります。
イノシシが萩(7月)に描かれる理由

7月の札に描かれているのは萩(はぎ)の中に身を下ろすイノシシ。
ここで萩とは秋の七草の一つで、マメ科の植物です。
日本各地の山野でごくふつうに見ることができます。
古くから日本人にとって萩は身近な存在だったのか、万葉集には萩の歌が141つも掲載されています。
これは万葉集に出てくる花の中で一番多いのだとか。
このように、萩は身近な植物でもあり、文学的な題材でもあったんですね。
ではなぜ萩とイノシシが一緒に描かれているのでしょうか?
その理由の一つとして挙げられるのが、ふすいのとこという言葉。
ふすいのとこ??

徒然草にこういった一節があります。
和歌こそ、なほをかしきものなれ。あやしのしづ・山がつのしわざも、言ひ出でつればおもしろく、おそろしき猪(い)のししも、「臥(ふ)す猪の床(とこ)」と言へば、やさしくなりぬ。
兼好法師「徒然草」第十四段
出てきました!ふす猪の床!
こちらの現代語訳を見てみましょう。
和訳:和歌はやはり興味深いものだ。身分の低い下民や木こりのような賤しい者がやることも、和歌に詠めば情緒があり、おそろしいイノシシも「臥す猪猪の床」と言えば優雅になる。
語呂の良さはもちろんのことですが、確かに、優雅です(笑)
草で作ったベッドに身を埋めて「すー、すー」と寝ているイノシシの姿が想像できますね。
このように荒々しいイノシシと柔らかく優雅な植物の対比として、萩とイノシシが一緒に描かれるようになったと考えられます。
なぜ10月は鹿で、7月はイノシシなのか
鹿と紅葉、イノシシと萩は分かったけど、なぜ10月、7月なの?
大前提として、現在と江戸時代とでは暦(こよみ)が違うため注意が必要です。
現在は太陽の動きをもとに暦を作っているのですが、この太陽暦は明治6年に採用されたもの。
それ以前は月の満ち欠けをもとに、季節をあらわす太陽の動きを加味して作られた「太陰太陽暦」が使われていました。
よって1ヶ月半ほど、ずれが生じるのです。
- 旧暦の7月は、現在の8月〜9月。
- 旧暦の10月は、現在の11月〜12月。
暦と花札に描かれた動植物との関係

ではこの暦と、描かれた動植物との関係はどういうものなのでしょう?
まず鹿やイノシシと季節性の関係といえば…。
鹿は春に出産し、夏に肉としての旬を迎え、秋にオスがメスを奪い合い闘い、冬に角が抜け落ち…といったサイクルです。
イノシシは、春か秋に妊娠して一度の出産で4頭ほどの子供を産みます。冬眠はせず、年中、活動しています。
このように鹿やイノシシの生態サイクルと花札の月にはこれといった関連はありません。

一方、萩の開花時期は6月から10月です。
また紅葉がきれいに色づくのは11月ごろ。
ちょうど開花時期や見頃と花札の月が重なっています。
「花札」というくらいですから、花札に描かれているのは12月分12種類の季節の草花。
その草花に、鶴や幕、盃(さかずき)、イノシシや鹿といった動物が描かれます。(動物が登場しない月もあります)
よって季節の草花として7月の札に萩、10月の札に紅葉が描かれて、それに紐づく動物が描かれたと考えると自然でしょう。
そのエピソードとして、先ほどの「三作の物語」や「臥す猪の床」というお話があるのだと私は考えました。
他にも野生動物をモチーフにした文学作品をこちらにまとめてみたので、気になった方はチェックしてみてください。

まとめ
花札に出てくる動物は、8種類です。
犬や猫などを差し置いて、鹿とイノシシが選ばれた。
それほど鹿とイノシシは身近な存在だったのではないでしょうか?
このように、鹿とイノシシは意外と生活の近くに潜んでいます。
花札は、ネットや100円ショップでも買えますので、ぜひやってみてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!